
八日市・護国町並み保存センター
ここは、地域住む人たちが主役になって地域づくりを進め、町並み保存のこれからを楽しく考える場所です。
八日市・護国地区町並保存会の事務所を兼ね備え、各種会合を開いたり、建築の修理に関する相談窓口
にもなっています。また、保存地区の北玄関として町並み保存に関する資料を掲示し、同時に観光に関する インフォメーションも行っています。
|
内子町は、江戸時代から明治時代にかけて、和紙と木蝋でで栄えた町です。その当時の面影を残す八日市・護国地区の町並みは、今も美しい佇まいを見せ、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。町では、現在、町並み保存運動に続く村並み保存運動を展開しています。
|
|
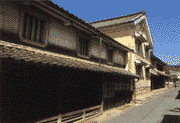
|
|